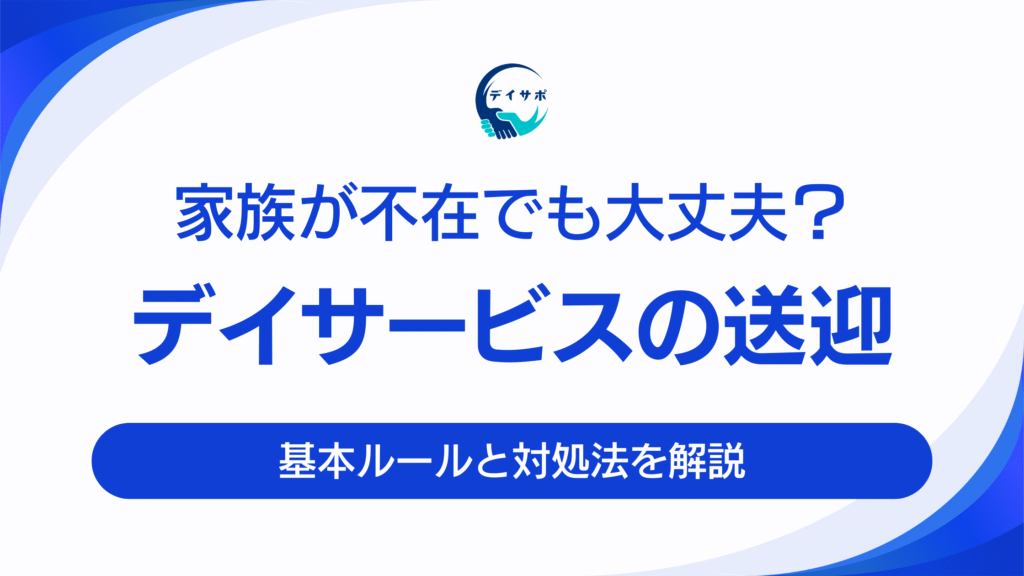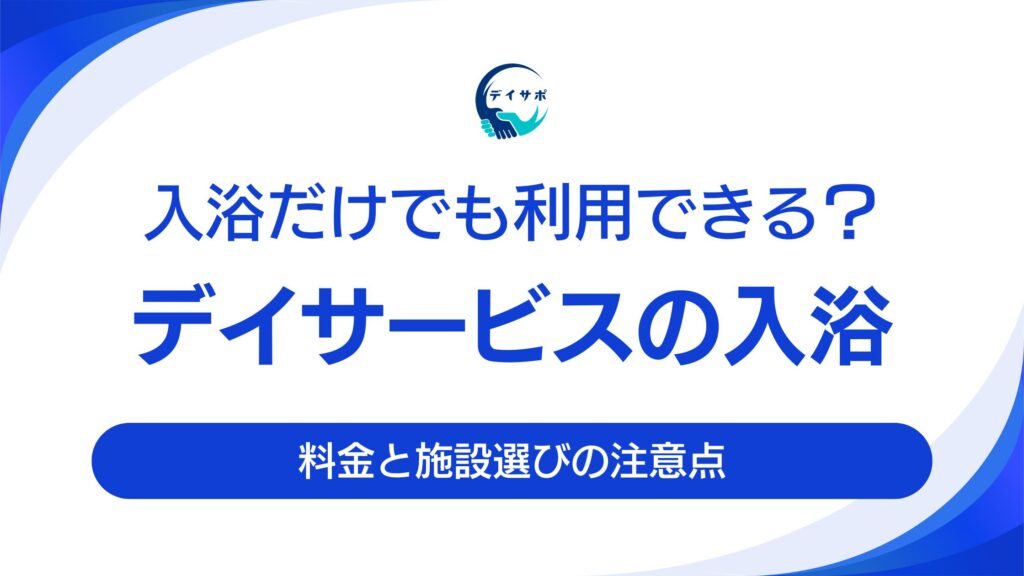デイサービスの現場では、職員への暴言や他の利用者への嫌がらせ、ルール違反など、いわゆる“迷惑な利用者”への対応に悩むケースがあります。とある調査では、約4割のデイサービス職員がハラスメント被害を経験していると報告されています。
介護現場のハラスメントは介護業界が抱える大きな課題のひとつです。「迷惑な利用者の利用を断ってもいいものか?」「ハラスメントを繰り返す利用者から職員を守るにはどうすればいいのか?」など、対応に悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
本記事記事の中では、デイサービス運営歴10年以上の筆者が、過去の経験や知識をもとに、さまざまなトラブルの事例と解決策を紹介します。この記事が、事業所運営に悩むデイサービス経営者のヒントになれば嬉しいです。
筆者

野田晃司
デイサービス所長/作業療法士国家資格取得後に病院へ勤務し、介護事業を行う企業へ入社。立ち上げたデイサービスが、わずか10ヶ月で登録者数100名超えるほどの人気施設に。施設のInstagramフォロワーが40万人を突破。現在は、マーケティングライターとしてセールスコピーやSEO記事の執筆をしつつ、デイサービス運営について講演会やセミナーで登壇している。
詳しいプロフィールを見る
迷惑な利用者に悩まされるデイサービスは多い

厚生労働省が平成30年に公表した「介護現場におけるハラスメントに関する調査研究報告書」では、通所介護職員の中で直近1年以内に利用者からハラスメントを受けた経験がある方は46%、過去に一度でも受けたことがある方は36%という結果が示されています。
厚生労働省のデータから、デイサービスをはじめとする介護現場では、利用者によるハラスメントやトラブル行為へ適切に対処することが重要だと言えるでしょう。本記事では、筆者自身が介護現場で経験した事例とともに、迷惑な利用者への対応策を詳しく解説していきます。
参照元:厚生労働省|介護現場におけるハラスメントに関する調査研究報告書
事例1:職員へ不適切な言葉や行動を繰り返す

厚生労働省のデータによるとハラスメントを受けたデイサービス職員の73.4%が精神的暴力(暴言や威圧的な態度)を受けたと回答しています。ここでは、職員への不適切な言葉や行動を繰り返す利用者の事例と解決策をご紹介します。
シチュエーション
男性の利用者Aさんが、特定のデイサービス職員に対して暴言を繰り返し、ときには物を投げたり叩いたりと暴力的な行動をすることもありました。施設管理者が注意するものの、まともに対応してもらえず、職員は精神的に疲弊していきました。
Aさんは、他の利用者には穏やかな態度を見せていたため、外部からは問題が見えにくく、施設側も対応に困る事態に。さらにハラスメント行為がエスカレートし続け、職員の離職も懸念される状況になりました。
解決策
まず、最初に情報を整理しましょう。特定のシーンや言動だけを切り取って考えると、根本的な解決策を見落とすこともあります。たとえば、問題行動の内容や頻度を記録して、客観的データを蓄積していくと良いでしょう。
厚生労働省の資料「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル令和4(2022)年3月改訂」では、ハラスメント対策の基本的な考え方として以下のように記載しています。
ハラスメントが起こった要因の分析が大切であること
できるだけ正確な事実確認を行う等して要因分析を行い、施設・事業所全体でよく議論して、ケースに沿った対策を立てていくこと。
*一方で、ハラスメントが発生する状況によっては、正確な事実確認には限界があるということを前提に、必要な対策を講じることも必要です。ハラスメントのリスク要因を参考に、事前に実施可能な対策がないかを検討しましょう。
引用:厚生労働省|介護現場におけるハラスメント対策マニュアル令和4(2022)年3月改訂
ハラスメント発生時には、チーム全体で共有し、特定の職員に負担が偏らない体制を整備することが大切です。また、利用者本人に対しては、ケアマネジャーや家族を交えた話し合いの場を設け、施設側の姿勢として「ハラスメント行為は受け入れられない」と明確に伝達しましょう。施設としての対応方針を丁寧に説明することで、利用者の態度に一定の改善が見られる可能性があります。
事例2:施設のルールを守れない

デイサービスでは、施設の安全・衛生・秩序を守るためにさまざまなルールが設けられています。しかし中には、施設のルールを守れない利用者も存在し、対応に苦慮するケースがあります。ルールを守れない利用者がいる場合、施設運営に支障をきたすだけでなく、他利用者へ悪影響を及ぼす可能性もあるため、早期の対応が求められます。
シチュエーション
利用者Bさんは、施設内での食べ物のやり取りが禁止されているにもかかわらず、他の利用者へお菓子を配っていました。また、持ち込み禁止の食べ物を隠れて食べたり、許可なく外に出たりするなど、安全管理上の問題も発生。職員がルールを説明しても「自分の自由だ」と聞き入れず、対応に追われる日々が続きました。
また、職員の見ていない時間を見計らって、糖尿病でカロリー制限をしている利用者へお菓子を渡すこともあり、他利用者の健康状態に悪い影響を及ぼす可能性もありました。
解決策
施設のルールを守ってくれない利用者に対して最初にすべきことは、施設のルールがなぜ必要なのかを理解してもらうことです。ルールを守れない迷惑な利用者だと決めつけず、丁寧に説明することでこちらのお願いを聞き入れてくれる可能性もあります。ルールについて丁寧に説明したとしても改善が見られない場合は、家族やケアマネジャーを交えた面談を行いましょう。
面談では、ルールが必要なことを伝えるだけでなく、利用契約書や重要事項説明書の内容について再度確認し、話し合いの内容を記録に残すことが大切です。こうした話し合いの記録を残し、施設職員で情報を共有することで、その後一貫性を持って対応できるようになり、徐々に利用者の行動が改善される可能性があります。
事例3:他の利用者へ嫌がらせをする

デイサービスで起こるトラブルは、利用者対職員だけではありません。利用者同士で起こるトラブルを解決することも大切です。
たとえば、大声で怒鳴る、持ち物を隠す、身体的な接触を伴う嫌がらせなど、被害を受けた利用者の心身に大きな影響を及ぼす可能性があります。とくに精神的な不安を抱える利用者にとっては深刻な問題であり、施設全体の雰囲気にも悪影響を及ぼすため、早期の対応が求められます。
シチュエーション
利用者Cさんが、隣席の方に対して繰り返し暴言を吐き、隣席の利用者が不快な思いをするトラブルがありました。また、他の利用者に対しても、荷物に勝手に触れたり、突然罵声を浴びせたりと周囲の利用者が強いストレスを感じている状況でした。
さらに他利用者から「Cさんがいると怖くて利用できない」と相談されることもあり、ケアマネジャーからも対応を求められることに…。その後、スタッフによる注意を行うものの、反発的な態度を取り続け、改善の兆しが見られない状況が続きました。
解決策
まずは、施設が共用の場であることや、他利用者に対する配慮をして欲しいことを直接伝えましょう。特定の利用者とトラブルになる場合は、活動時間を分けたり、座席を離したりすることで落ち着くこともあります。そうした現場の対応で解決しない場合は、家族やケアマネジャーと連携し、対応方針を共有することが重要です。
厚生労働省の資料「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル令和4(2022)年3月改訂」では、ハラスメント対策の基本的な考え方として以下のように記載しています。
施設・事業所ですべてを抱え込まないこと
自らの施設・事業所内で対応できることには限界があるため、地域の他団体・機関とも必要に応じて連携すること。
引用:厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル令和4(2022)年3月改訂」
家族やケアマネジャーと情報を共有することで、本人の意識を変えられる可能性もあります。とくに利用者同士のトラブルがエスカレートすると、他利用者の満足度が下がったり、利用停止になったりする可能性もあります。早期解決に向けて早めに対処することをおすすめします。
Cさんの場合は、家族やケアマネジャー、施設職員とあらゆるアイデアを出して対応しましたが、改善が見られませんでした。最終的には、他の利用者へ危害を加えそうになる事態も発生したため「利用をお断りする」という大変残念な結果となってしまいました。
迷惑な利用者を拒否することは可能

デイサービスは公共性の高い事業ですが、事業者側にも利用者を選ぶ権利があります。継続的な迷惑行為があり、他の利用者や職員の安全・業務に支障をきたす場合には、契約解除も検討可能です。ただし、施設側からハラスメントを理由に契約を解除する場合は正当な理由が必要です。厚生労働省の資料には、以下のように記載しています。
(7) ハラスメントを理由とする契約解除は「正当な理由」が必要であることを認識すること
⚫ 前提として、利用者やその家族等に対して、重要事項説明書の説明等によって、提供するサービスの目的、範囲及び方法に関して十分に説明を行い、その理解していただくこと、契約解除に至らないような努力・取組を事業所としてまず行うことが必要です。
⚫ このような努力や取組を行っていても、やむを得ず契約解除に至るケースもあるかもしれません。しかし、施設・事業所側からする契約解除には「正当な理由」(運営基準)が必要です。「正当な理由」の有無は個別具体的な事情によりますが、その判断にあたっては、
・ハラスメントによる結果の重大性
・ハラスメントの再発可能性
・契約解除以外のハラスメント防止方法の有無・可否及び契約解除による利用者の不利益の程度
…等を考慮する必要があります。
「正当な理由」に基づき契約を解除した場合であっても、契約解除に至った原因及び経緯を検討し、同様の事態を防止するための対策を講じましょう。
引用:厚生労働省|介護現場におけるハラスメント対策マニュアル令和4(2022)年3月改訂
正当な理由があれば、デイサービスの利用を拒否することは可能です。しかし、突然利用を拒否してしまうとトラブルの原因となるため、まずは指導や改善の機会を設け、記録を残しながら段階的に対応しましょう。また、最終的な判断は、ケアマネジャーや家族とも連携のうえで慎重に行うことも大切です。施設としての運営方針と法的リスクのバランスが問われる難しい手続きであることを理解しておきましょう。
トラブルを解決するために重要なポイント

デイサービスにおける利用者とのトラブルは、職員や他の利用者に大きなストレスを与えます。放置すれば施設の雰囲気やサービスの質に悪影響を及ぼしかねません。こうした問題に冷静かつ的確に対処するためには、感情に流されず、事実を整理した上で対応策を講じることが重要です。ここでは、迷惑な利用者とのトラブルを最小限に抑えるための実践的なポイントを解説します。
冷静に現状を整理して解決策を検討する
利用者の迷惑行為が発生した際には、被害を受けた職員や利用者に寄り添うことが重要です。しかし、そうした方の意見に流されて感情的に問題を解決しようとすると、さらに状況が悪化する可能性もあります。まずは、一度冷静になって、客観的な視点から事実を整理することが重要です。
厚生労働省のハラスメント対応マニュアルでは、職員の心身への影響を最小限にするには「ハラスメントの状況把握と共有」が有効と記載されています。誰が、いつ、どこで、どのような行為を受けたのかを具体的に記録し、客観的に分析することで、施設として適切な対応方針を検討しやすくなります。
必要に応じて家族やケアマネへの協力を依頼する
迷惑行為が続く場合、施設単独で対応できる範囲には限界があります。そのため、家族やケアマネジャー、主治医、地域包括支援センターなど、関係機関と連携しながら解決策を模索することが重要です。
たとえば、過去の施設利用歴や生活歴からリスクを把握し、事前に専門職同士で対応方針を検討しておくと、トラブルを未然に回避できる可能性もあるでしょう。
事前にルールを説明して同意を得る
利用者の迷惑行為を未然に防止するためには、利用開始時の丁寧な説明が重要です。利用者やご家族に対して、重要事項説明書や契約書の内容を口頭でわかりやすく伝えることが大切です。
とくに「ハラスメントがあった場合には契約解除となる可能性がある」ということまで、具体的に説明しておくとトラブルを防ぎやすくなります。また、利用者や家族の理解度に応じて繰り返し周知し、必要に応じてケアマネや医師とも連携しながら対応しましょう。
迷惑な利用者から職員や施設を守るための対策

介護現場では、ハラスメントから職員を守るため、事前に対策を取っておくことも重要です。厚生労働省の資料には、以下のポイントを重要視するように記載されています。
- ハラスメントに対する施設・事業所としての基本方針の決定・周知
- マニュアル等の作成・共有
- 相談しやすい職場環境づくり、相談窓口の設置
- 介護サービスの目的及び範囲等へのしっかりとした理解と統一
- 利用者・家族等に対する周知
- 利用者や家族等に関する情報の収集とそれを踏まえた担当職員の配置・申し送り
- サービス種別や介護現場の状況を踏まえた対策の実施
- 利用者や家族等からの苦情に対する適切な対応との連携
- 発生した場合の対応
- 管理者等への過度な負担の回避
- PDCA(サイクルの考え方を応用した対策等の更新、再発防止策の検討)
引用:厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル令和4(2022)年3月改訂」
具体的な施策としては、施設内の死角によって1対1になる状況を避ける環境作りや、職員の個人情報を不用意に伝えないなどの配慮が求められます。さらに、リスクが高いと判断されるケースでは、担当職員のマッチングや情報共有を徹底することも有効です。また、契約書に迷惑行為に対する事業所の対応方針を明記することは、利用者や家族による迷惑行為への抑止力となります。
まとめ|迷惑な利用者への対策を準備しておきましょう
職員や他の利用者の安全と安心を守るためには、迷惑行為を行う利用者への対応が重要です。トラブルが起きてから対処法を探すのではなく、事前にルールを決めておくと良いでしょう。
トラブルが発生した際には、まず冷静に状況を把握し、記録や情報共有を徹底することが大切です。そのうえで、家族やケアマネとの連携、必要な説明やルールの周知を行いましょう。厚生労働省は、施設全体の方針としてハラスメント対策をしておくべきと考えており、対応マニュアルも公開しています。
デイサービス経営者は、トラブルが発生してから対処法を模索するのではなく、厚生労働省の資料も参考にしつつ、事前に対応策を準備しておくと良いでしょう。